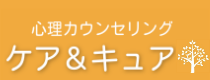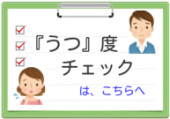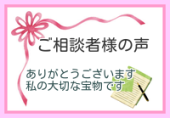家族がうつ病になったら?回復を早める接し方、病院との付き合い方
うつ病の克服には、充分な休養や治療の他、身近な人、特に家族の適切な配慮とサポートが大きな効果をもたらします。
しかし実際に、家族がうつ病を発症したら、どう対応すればよいかわからず、混乱してしまうこともあるでしょう。「何とかしなければ…」と気負いすぎて、自分自身が大きな負担を抱えることにもなりえます。
「自分の一言が禁句で、症状の悪化に繋がったら…」と不安になったりすることもあるかもしれません。
 うつ病の克服には、焦らずじっくり取り組む姿勢が大切ですし、自分の状態を客観的に見つめることや、生活習慣の改善も必要になってきます。
うつ病の克服には、焦らずじっくり取り組む姿勢が大切ですし、自分の状態を客観的に見つめることや、生活習慣の改善も必要になってきます。
したがって、家族が病気を冷静に受けとめ、本人の様子をよく観察しながら適切にサポートすることは、うつ病の回復を早めることに繋がります。
実際にうつ病を克服され、その後も再発を繰り返すことなく社会復帰を果たされている方のほとんどは、ご家族がとても大きな支えとなり、それを本人も自覚してご家族に感謝していらっしゃいます。
私がお話を伺う場合も、うつ病に限らずですが、病気を克服するために活用できる有力な“資源”として、ご家族からのサポートを受けられそうかどうか、聞かせていただくことにしています。
 「あんなこともあったね」と、いつの日か笑いながら話せる日が来る。 そんな希望を持ちながら、うつ病を発症したご家族が少しでも心穏やかに回復に向かえるように、また、それを支える自分自身も安定した心で接することができるようにはどうすればよいか、ご紹介いたします。
「あんなこともあったね」と、いつの日か笑いながら話せる日が来る。 そんな希望を持ちながら、うつ病を発症したご家族が少しでも心穏やかに回復に向かえるように、また、それを支える自分自身も安定した心で接することができるようにはどうすればよいか、ご紹介いたします。
目次
1.うつ病の家族とのコミュニケーションで留意する点
1-1.話の聴き方‐否定せず、気持ちを受け止める
うつ病を発症すると、抑うつ気分などの症状のせいで、周囲の人間に攻撃的な言葉をぶつけてしまうことがあります。家族のちょっとした言葉に過敏に反応して、激しく自責の念に駆られることや、怒りや失望をあらわにすることも多いでしょう。
逆に、「家族に迷惑をかけたくない」という気遣いや「どうせ理解してもらえない、助けてもらえない」というネガティブな考えのために、サポートを拒絶して自分の殻に閉じこもることもあります。
しかし、だからといって家族が本人を気遣いすぎて、腫れ物に触るような扱いをして何時間も接する時間を持たずに放置しておくことは、あまり良くありません。
本人を気遣いながらも“普通に”、“いつも通り”振る舞うことが、本人の安心に繋がります。
そしてその安心こそが、心の安定に繋がり、回復への大きなエネルギーを生み出すのです。
 とは言え、本人の気持ちが不安定でひどく惑乱しているようなときには、「うるさい!」と暴言を吐いたり、「ひとりにして!」と自室に閉じこもってしまうようなこともあります。
とは言え、本人の気持ちが不安定でひどく惑乱しているようなときには、「うるさい!」と暴言を吐いたり、「ひとりにして!」と自室に閉じこもってしまうようなこともあります。
そういうときには、無理に話そうとせず、様子を見ましょう。 本人も少し落ち着いてくると、自分の気持ちを聞いてもらいたくなるものだと思います。
本人が話を聴いてほしそうであれば、「そんなことがあったんだ」「大変だったね」と共感しながら耳を傾けます。 ただ話を聴いてくれるだけでも、随分と心が休まるものです。
「そんなこと言ったって仕方ないでしょう?」等、言いたくなることもあるでしょうが、決して断定・否定をすることなく、『そう考え、そう感じている本人』を尊重し、受け入れることが大切です。
本人が、誰かを非難したりしても、それをたしなめたり叱ったりするのではなく、 「そうか、そんな風に思うんだね」と、認めてあげること。 「もっとこうすべきだったのに」と正論をぶつけて断じるのではなく、 「こういうやり方もあったかもしれないね」と、柔らかく示してみること。
本人の考えを正そうとして自分の意見を言いたくなったり、もっと前向きな発言を引き出したくなるかもしれませんが、本人のエネルギーが充分回復するまで待ちましょう。
1-2.声のかけ方‐本人の不安やプレッシャーを増幅させないように
うつ病の人に「がんばれ」と言ってはいけないというのはよく聞くかもしれませんが、なぜ言ってはいけないのでしょうか。
その理由は、うつ病はがんばりすぎたために心身が疲弊している状態なので、更なる「がんばり」を課すことは本人にとっては絶望に近く、叱咤されているようにしか聴こえないことが多いためです。
もうひとつには、うつ病を発症すると、自分自身に対する自信が非常に低い状態になるので、「周囲の期待に応えられない自分」を責め、「なんて自分はダメなんだ」とさらに自信をなくすことに繋がるためです。
「一家の大黒柱なんだから」
「お母さんがそんなに弱いことでどうするの。子供がかわいそうよ」
「もっと大変な思いをして仕事をしている人だっているよ」
たとえ本人を励まそうとする意図であっても、プレッシャーをかけたり、他の人と比較するような言葉には慎重になる必要があります。
ご家族がじっくり話を聞いてあげることは、うつ病の回復に大きな効果がありますが、ずっと一緒にいて話を聞き続けることは、聞く側にはとても負担になることです。
必ずひとりの時間を確保するようにして、自分の心の安定を崩さないようにすることが大事です。その際は、
「ご飯の後で話そうね」
「30分くらい買い物に行ってくるので、その後話そう」
「今日は○時くらいに仕事から帰ってくるよ」
といったように前もって話しておくことで、本人の不安を取り除いてあげましょう。
また、調子の悪いことや、できていないことを指摘するのではなく、良くなってきていること、できていることをそれとなく伝えてあげると、本人も自分が少しずつでも普段通りの自分に戻れている実感が得られます。 「また昼まで寝ていたね」ではなく「昨日よりも早く起きられたね」というようにです。 (あまり大げさに頻繁に伝えると、却って本人の重荷になるので注意が必要です)
1-3.「死にたい」「どうせ治らない」…そんな言葉を口にされたら
うつ病の症状として顕著に見られるもののひとつに、『自殺念慮』があります。
気持ちが沈み、あまりにもつらいため「死んだほうがましだ」「この世から消えてしまいたい」と考えるようになります。ほとんどの人が一度は「死にたい」と考えるようです。
うつ病の家族から、「もう生きていたくない」「死にたい」という言葉を口にされるかもしれません。
そんなとき、動揺して「そんなこと言わないで!」と感情的に訴えたり、「死にたいなどと言ってはいけない。家族のことも考えて」と説教したりすることは、本人にとっては“死にたいくらいつらい気持ちを抱いている自分”を否定され、行動を制限されるように感じます。
 「これは病気のせいであり、本心ではないのだ」と自分に言い聞かせ、気持ちを落ち着かせることが肝心です。
「これは病気のせいであり、本心ではないのだ」と自分に言い聞かせ、気持ちを落ち着かせることが肝心です。
「死にたいと思うほど、今つらいんだね」と、本人の気持ちに寄り添いましょう。
そして、「あなたがもしいなくなってしまったら、私はとても悲しい。いつも、何があっても私はあなたの味方だから」と、落ち着いて伝えてあげましょう。
2.医師・薬との付き合い方
2-1.経過をよく観察し、本人の状態に合わせたサポートを
うつ病になると、大きく2つのケースに分かれるようです。
① 医師や薬に頼りきり、薬への依存から抜け出せなくなる人
② 病院に行きたがらない人
うつ病の症状自体は、適切に処方された薬を服用することで緩和します。十分な休養と併せて、回復のための土台を作ってくれるでしょう。
しかし、『薬を飲む』ことに依存してしまい、いつの間にかものすごい量の薬を処方されても疑問を持たずに服用し続けるというケースがあります。
それによって回復に向かっているのであれば良いのですが、副作用も見逃せませんし、ある程度回復しても、薬を飲まないことに不安を覚えて何年も飲み続けることになりかねません。
ご家族としては、 ・むやみと薬が増えていないか ・薬を飲んだ後に、状態が悪くなっているようなことはないか それとなくチェックしてあげるとよいでしょう。
 もしそのような傾向があれば、本人があまり嫌がるようでなければ、家族が診察に付き添って、本人が医師に自分の状態を正しく伝えられるようにフォローしてあげると良いでしょう。
もしそのような傾向があれば、本人があまり嫌がるようでなければ、家族が診察に付き添って、本人が医師に自分の状態を正しく伝えられるようにフォローしてあげると良いでしょう。
ただしこの際に、本人の発言を遮ったり真っ向から否定したりして、本人の自信を無くすようなことは避けるようにしましょう。
「医師が話をじっくり聞いてくれない」と、不満を持つ人も多いようですが、本来、医師は『症状に合わせて薬を処方する』のが本分ですので、患者の話を充分に聞いてあげることができないのが現状かもしれません。
そういうことからも、病院で適切に薬を処方してもらいながら、カウンセリングを並行して受けるというのはとても効果があります。実際、うつ病の再発が最も少ないのは、このやり方を実践した場合です。
2-2.病院を勧めるときは、本人の意思を尊重して
②の、病院に行きたがらないケースですが、 明らかに様子がいつもと違うと家族が感じても、本人の意思を考慮せず無理やり病院に連れていくことは、家族に対する不信感が芽生えてしまうので、注意が必要です。
あくまでも本人の意思を尊重している姿勢を保ち、様子を見ながら、時期をみて「行ってみない?きっと少しでもつらい症状が和らぐと思うから」と声をかけてあげるとよいでしょう。
本人が通いやすそうで、信頼が置けそうな病院はどこか、アンテナを立てて探しておくことも家族にできるサポートのひとつかもしれません。
3.うつ病の家族を支える立場の方々に、心がけていただきたいこと
3-1.家族がうつ病になったことを、どう受け止めるか
家族がうつ病になると、なかなかその現実が受け入れがたく、「どうしてこんなことになってしまったのか」と原因を突き止めようとしたり、「もっと妻を(夫を)かまってあげていたら、ケアしてあげていればよかった」と後悔して自分を責めることも多いようです。
他にも私がお聞きした中では、 「身内から、『夫であるあなたのせいだ』と言われた」、 「姑から『あなたがしっかりしないでどうするの。彼が治るかどうかはあなたにかかっているんだから』と叱咤され、涙があふれた」といったケースもありました。
うつ病に限らず、精神疾患と呼ばれるものは、単一の要因で発症するものとは言えません。
本人の性格傾向や環境要因、体調などの掛け算で引き起こされるものです。 決して家族が罪悪感に押しつぶされる必要はありません。
「これからどうすればいい?」と不安になることもあるかもしれません。しかし、ここは心をなるべく落ち着かせ、冷静に受け止めることが大切です。
3-2.まずは支える側の『心の土台』を安定させること
うつ病の克服には、長期間の取り組みが必要になりますし、うつ病の症状のせいで人が変わってしまったようになった家族を支えることは、かなりの精神的・肉体的な負担がかかります。
実際に、うつ病は身近な人にうつりやすいと言われており、例えば夫がうつ病になり、必死でサポートしてきた妻も発症するといったようなことが多くあります。 ただでさえ、うつ病の家族のネガティブな言動に接しているにも関わらず、それに加えて、自分自身を精神的に追い詰めてしまう傾向があります。
「早く治ってほしい」という焦り、
「なぜこの人はこんな考え方しかできないのか。もううんざり。いい加減にしてほしい」という憤りや失望、そして、
「こんなふうに思う自分は何てひどいんだ。そもそも自分の関わり方が悪かったから、こんなことになったのではないか」という罪悪感がせめぎ合うようです。
家族のこのような葛藤は、少なからず本人にも伝わり、
「家族にこんなに迷惑をかけている。こんなに困らせている。なんて私はダメ人間なんだ」と余計自分を追い込むことにもなってしまいます。
うつ病に限らず、心の病気の回復のためには、安心できる環境を整えることが何よりも重要になります。 本人の状態で一喜一憂せず、調子が良さそうであれば「良かったな」、悪そうなら「こんな日もあるな」と、ゆったりと構えることが肝要です。
どんな状態でも自分を受け入れてくれると感じることができれば、本人にとって家族は、『揺るぎない、安心をくれる場所』であることができます。
そのためにも、自分自身がリフレッシュする時間を積極的に作ったり、抱え込ま ずに専門家に相談したりするなどして、『心の土台』を安定させることが大切です。
ずに専門家に相談したりするなどして、『心の土台』を安定させることが大切です。
趣味にいそしむことや、友人とお茶に出かけることも良いでしょう。
「私だけこんなに楽しんでしまって申し訳ない」と外出を極端に控えたり、今まで楽しんできた趣味を手放したりしてしまうと、気持ちが疲弊してしまってうつ病の家族を支えきれず、共倒れを引き起こしかねません。
家族である自分自身の『心の土台』が安定してこそ、本人に安心を感じてもらうことができ、うつ病を克服するエネルギーの源となります。
この記事に関連する記事一覧
-

私はアダルトチルドレン?と思ったら…その傾向と克服への道筋とは
-

今日から使える!アロマセラピーで手軽にストレスを解消
-

こんなこともうつ病の原因に?人生に潜むストレス、着目するのは『変化』
-

うつ病の症状とは/心と身体に表れる10の症状
-

家族がうつ病になったら?回復を早める接し方、病院との付き合い方
あなたの心やからだの状態を
チェックしてみませんか。
簡単に自己診断していただけます↑
これまでに頂戴したメッセージを
ご紹介しております
是非ご覧ください↑
- 営業時間 および メールカウンセリングにつきまして
- 対面でのご相談業務の再開につきまして
- HOME
- カウンセラー紹介
- ご相談内容
- ケア&キュアのカウンセリングとは
- サービス・料金
- ご予約・お問い合わせ
- うつ病度チェック
- ご相談者様の声
- よくあるお問い合わせ
- 個人情報保護方針
- サイトマップ
- リンク